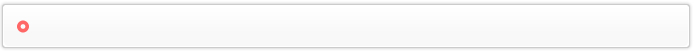
新人ナースのためのかんたんモニター心電図の見方ハンドブック
 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
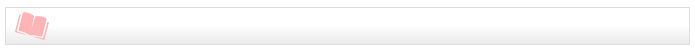
書籍概要
「だいたいしかわからない…?」「モニター心電図の何をみて、どう対応したらいいの?」
「あれ?と思ったら、ベッドサイドへ!」
ナースだから伝えられるかんたんアプローチで、モニター心電図の見方をやさしく解説。
患者の状態を把握して、適切な対応がとれるようになるためのトレーニングブック。
「あれ?と思ったら、ベッドサイドへ!」
ナースだから伝えられるかんたんアプローチで、モニター心電図の見方をやさしく解説。
患者の状態を把握して、適切な対応がとれるようになるためのトレーニングブック。
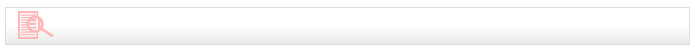
書籍目次詳細
目次
はじめに
第1章 モニター心電図 これだけは知っておこう!
1.そもそも心電図って何?
2.複数の方向から眺めた波形って何? まず12誘導心電図の話
3.モニター心電図の電極の貼り方
4.モニター心電図の見方 まず、心拍数をみよう
5.心拍数50~100回/分で正常な波形 みんながサイナスっていうやつ
6.心拍数100~120回/分くらい みんながタキッてるっていうやつ
7.だいたい心拍数90~130回/分くらい サイナスじゃなさそうな頻脈
8.心拍数150回/分くらい
9.心拍数50回/分以下 みんながブラディーっていうやつ(心拍数40回/分台の場合)
10.心拍数50回/分以下 みんながブラディーっていうやつ(心拍数30回/分台の場合)
11.心電図がうまくとれない! こんなときどうする?
12.脈がバラバラのやつ
13.アレスト! 心停止!
第2章 モニター心電図 こんなときどうする?
1.アラームが鳴ったときどうする?
2.異常な波形が出たときどうする?
症例1 洞調律
症例2 洞性頻脈-疼痛
症例3 洞性頻脈-脱水
症例4 洞性頻脈-肺塞栓症
症例5 発作性上室性頻拍
症例6 洞不全症候群
症例7 完全房室ブロック
症例8 心房期外収縮
症例9 心室期外収縮
症例10 心房細動
症例11 心筋梗塞
症例12 心停止
あとがき
はじめに
第1章 モニター心電図 これだけは知っておこう!
1.そもそも心電図って何?
2.複数の方向から眺めた波形って何? まず12誘導心電図の話
3.モニター心電図の電極の貼り方
4.モニター心電図の見方 まず、心拍数をみよう
5.心拍数50~100回/分で正常な波形 みんながサイナスっていうやつ
6.心拍数100~120回/分くらい みんながタキッてるっていうやつ
7.だいたい心拍数90~130回/分くらい サイナスじゃなさそうな頻脈
8.心拍数150回/分くらい
9.心拍数50回/分以下 みんながブラディーっていうやつ(心拍数40回/分台の場合)
10.心拍数50回/分以下 みんながブラディーっていうやつ(心拍数30回/分台の場合)
11.心電図がうまくとれない! こんなときどうする?
12.脈がバラバラのやつ
13.アレスト! 心停止!
第2章 モニター心電図 こんなときどうする?
1.アラームが鳴ったときどうする?
2.異常な波形が出たときどうする?
症例1 洞調律
症例2 洞性頻脈-疼痛
症例3 洞性頻脈-脱水
症例4 洞性頻脈-肺塞栓症
症例5 発作性上室性頻拍
症例6 洞不全症候群
症例7 完全房室ブロック
症例8 心房期外収縮
症例9 心室期外収縮
症例10 心房細動
症例11 心筋梗塞
症例12 心停止
あとがき
続きを読む
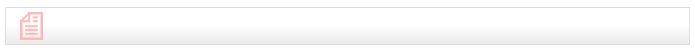
序文・はじめに・あとがき 等
あとがき
私が看護師になったばかりのころ、病棟で鳴り響くモニター心電図のアラームの音が恐怖でしょうがありませんでした。
なんで鳴っているのか、どうすればいいのかわからなくて、先輩にも怖くて聞けないし……。
とにかく、「私の勤務中には、何ごとも起きないでくれー」って毎日祈っていました。
それで、とりあえず先輩たちのやっていることを盗もうと思い、先輩たちの話していることに耳を傾けてみると、
「頻脈アラーム頻回になっていましたが、血圧は下がりませんでした」
「PVC 散発がみられましたが、胸部不快ありません」
などなど……。
私は、そこで不整脈というのは、胸部不快感がなくて、血圧が下がらなければいいんだ! ということを学びました。でも、本当にそれでいいんだろうか?
そう思って、心電図の本を読んでみました。
「AVRT は心室から心房へ逆行性に伝導する経路により、心室の興奮が心房へ伝わり循環することで頻脈をきたし、AVNRT はAV node 内にリエントリー回路を有し、node 内で伝導が循環するため心房、心室を興奮させ続け頻脈をきたす……」???
ぜんぜん意味がわからない‼
それよりなにより、それをどう看護につなげればよいのか全くわかりませんでした。
それから何十年もたち、診療看護師としてはたらいている今思うことは、たとえば、頻脈がPSVT だろうと、AT だろうと、AF だろうと、どれでもよくて、さらに心臓の中のどこを信号がグルグルしているかなどは、とりあえずどうでもいいってこと。
アラームが鳴ったとき、どう考えればよいのかを知らないから怖いんです。
だから、どう考えて、どう患者さんに対応すればよいかをちゃんと知っておくこと、それをくり返し実行していけばアラームは怖くなくなるっていうことです。
本書では、まず「あれ? と思ったらベッドサイド!」です。
そしてみなさんには、異常な波形をみつけたときの「型」(アルゴリズム)を覚えてもらい、それに沿って考え患者さんに対応できるよう事例をあげながらアプローチしてみました。
そのうえで、心電図の見方―心臓の信号がどこをグルグルしているとか、どこがブルブルしてるとかを改めて学んでもらえたら、さらに理解が深まると思います。
そして、異常をみつけたら先輩や医師に報告。それで完璧です。
もう、アラームなんて怖くない! ステキなナースになってくださいね。
2025年6月
本郷葉子
私が看護師になったばかりのころ、病棟で鳴り響くモニター心電図のアラームの音が恐怖でしょうがありませんでした。
なんで鳴っているのか、どうすればいいのかわからなくて、先輩にも怖くて聞けないし……。
とにかく、「私の勤務中には、何ごとも起きないでくれー」って毎日祈っていました。
それで、とりあえず先輩たちのやっていることを盗もうと思い、先輩たちの話していることに耳を傾けてみると、
「頻脈アラーム頻回になっていましたが、血圧は下がりませんでした」
「PVC 散発がみられましたが、胸部不快ありません」
などなど……。
私は、そこで不整脈というのは、胸部不快感がなくて、血圧が下がらなければいいんだ! ということを学びました。でも、本当にそれでいいんだろうか?
そう思って、心電図の本を読んでみました。
「AVRT は心室から心房へ逆行性に伝導する経路により、心室の興奮が心房へ伝わり循環することで頻脈をきたし、AVNRT はAV node 内にリエントリー回路を有し、node 内で伝導が循環するため心房、心室を興奮させ続け頻脈をきたす……」???
ぜんぜん意味がわからない‼
それよりなにより、それをどう看護につなげればよいのか全くわかりませんでした。
それから何十年もたち、診療看護師としてはたらいている今思うことは、たとえば、頻脈がPSVT だろうと、AT だろうと、AF だろうと、どれでもよくて、さらに心臓の中のどこを信号がグルグルしているかなどは、とりあえずどうでもいいってこと。
アラームが鳴ったとき、どう考えればよいのかを知らないから怖いんです。
だから、どう考えて、どう患者さんに対応すればよいかをちゃんと知っておくこと、それをくり返し実行していけばアラームは怖くなくなるっていうことです。
本書では、まず「あれ? と思ったらベッドサイド!」です。
そしてみなさんには、異常な波形をみつけたときの「型」(アルゴリズム)を覚えてもらい、それに沿って考え患者さんに対応できるよう事例をあげながらアプローチしてみました。
そのうえで、心電図の見方―心臓の信号がどこをグルグルしているとか、どこがブルブルしてるとかを改めて学んでもらえたら、さらに理解が深まると思います。
そして、異常をみつけたら先輩や医師に報告。それで完璧です。
もう、アラームなんて怖くない! ステキなナースになってくださいね。
2025年6月
本郷葉子
続きを読む
