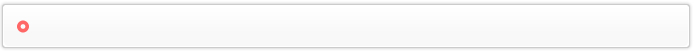
図解ワンポイント解剖学 人体の構造と機能
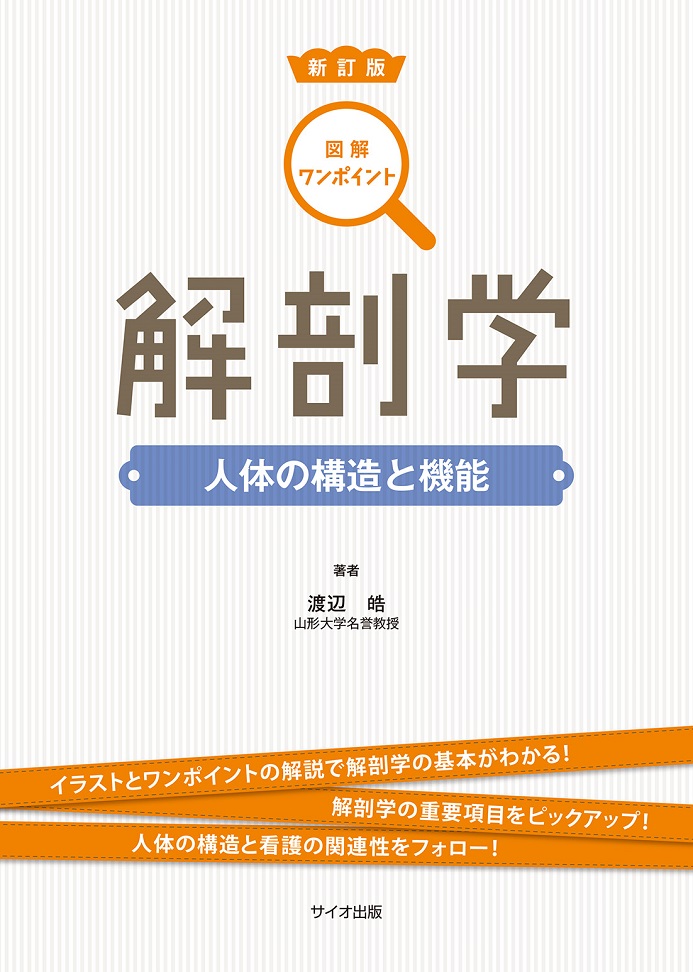 |
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
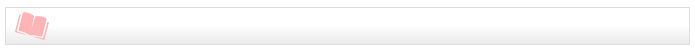
書籍概要
イラストとワンポイントの解説で、解剖学のエッセンスがわかる!解剖学の重要項目をピックアップして、1冊に凝縮した解剖学テキスト。Nursing Eye(看護の視点)で、「人体の構造」と「看護」の関連性が明確に理解できる、また、各章の「到達目標」で学習の目的がわかる。
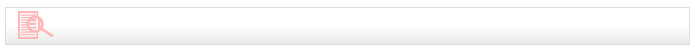
書籍目次詳細
【主な内容】 Chapter ・ 細胞、組織と器官 1.細胞 2.組織 3.器官 Chapter ・ 骨格系 1.骨格の役割と骨組織 2.骨の発生と成長 3.軟骨組織・関節と靭帯 4.頭部の骨 5.体幹の骨 6.体幹と上肢をつなぐ骨 7.上肢の骨 8.体幹と下肢をつなぐ骨・骨盤をつくる骨 9.下肢の骨 Chapter ・ 筋系 1.骨格筋 2.頭部の筋 3.体幹の筋 4.背部の筋 5.上肢の筋 6.下肢の筋 Chapter ・ 循環器系 1.循環器系 2.心臓 3.血管系:動脈系 4.血管系:静脈系 5.胎児の循環系 6.リンパ系 7.血液 Chapter ・ 呼吸器系 1.呼吸器系 2.鼻と鼻腔 3.咽頭と喉頭 4.気管・気管支 5.肺 Chapter ・ 消化器系 1.消化器系・消化管の構成 2.口腔 3.咽頭・食道 4.胃 5.小腸 6.大腸 7.肝臓 8.胆嚢・膵臓 9.体腔の構造 Chapter ・ 泌尿器系 1.泌尿器系・腎臓 2.尿管/膀胱 3.尿道 Chapter ・ 生殖器系 1.生殖器系・男性の生殖器 2.男性の生殖器 3.女性の生殖器 4.骨盤腔の性差・会陰の構造 Chapter ・ 内分泌器系 1.内分泌器官の特徴 2.下垂体 3.松果体・甲状腺・上皮小体 4.副腎 5.膵臓ランゲルハンス島・精巣と卵巣 Chapter ・ 神経系 1.神経系 2.中枢神経系 3.末梢神経系 Chapter ・ 感覚器系 1.感覚器・鼻腔と嗅覚器 2.視覚器 3.聴覚・平衡覚器 4.舌と味覚 5.皮膚と知覚
続きを読む
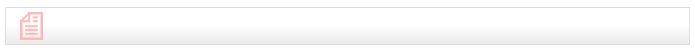
序文・はじめに・あとがき 等
はじめに 看護を学ぶ学生諸君は、初年度の新学期から専門基礎科目の1つとして人体構造学を履修することになる。これは人体の形と仕組みを理解する構造学が、いかなる医療分野においても最も基礎となる学問であることにほかならない。人体構造の基本を理解することなしに、人体の機能や病態を正しく理解することはできないからである。 筆者はこれまで、医学部で人体解剖の教育を担当する傍ら、看護師養成の大学や短大、専門学校などで30年間ほど人体構造の講義と解剖実習の教育にかかわってきた。1993年から定年退職するまでの15年間は、医学部看護学科で人体構造学の教育と研究に携わってきた。本書は、筆者がこれまで看護学を対象に行ってきた講義内容をもとにまとめたものである。人体構造を正しく理解してもらうために、できるだけ構造に忠実な図を掲載し、略図はあえて多用しなかった。読者諸君には、詳細な図を参考に略図を描く習慣を身につけてもらいたい。 一般的に学生諸君は、人体構造学は覚えることが多すぎる、難しすぎると感じているといわれる。筆者の経験では人体の構造について簡単な略図を描いて説明できる学生ほどよく理解し、興味を感じているようである。人体各部の名称を何の脈絡もなく覚えようとしたら、誰でも興味はもてないし、理解もしづらいであろう。 本書では、各章とも原則として見開き2ページにテーマをまとめ、図を参照しながら理解できるように編集してある。各章の冒頭には理解の目安となる到達目標を提示した。各章を読み始める前と、ひととおり学習した後に理解の程度を自己点検してもらいたい。 本書を出版するにあたり、看護系大学の教員として研究、教育に携わっている6名の皆さんにご協力をいただいた。この方々は筆者の在職中、大学院の研究室で学んだ修士生である。大学院修了後、それぞれが看護の臨床現場で経験を積み、現在、全国各地の看護大学で活躍中の第一線の研究教育者である。この方々の目をとおして本書がまとめられたことから、読者諸君には看護の実践に活用できる内容が簡潔に要約されている。さらに、各章に看護の臨床を意識した「Nursing Eye」を設け、内容を充実させた。また、看護師国家試験の過去問を各章に掲載してあるので、学生諸君が人体構造に関して身につけるべき基礎知識の自己点・氓ノ活用してもらえれば幸いである。 2015年12 月 執筆者代表 渡辺 皓(山形大学名誉教授) 改訂に寄せて 人の身体のつくりやしくみ、すなわち解剖を学べば学ぶほど、学ぶことが面白くなってきて、解剖学の知識が深まれば深まるほど、看護への理解が深まり、看護実践がより楽しく、やりがいのあるものになっていくことは、多くの看護師が確信していると思う。 看護師養成機関ではほとんどの場合、解剖学をはじめとする基礎専門科目教育が早期に組み込まれており、その後に看護の実際を学ぶことになるため、解剖を学ぶ動機づけが得難いのが現状である。看護教育の場に身を置く者としてだけでなく看護師として、学生の皆さんの先輩として、解剖を学ぶ意義をうまく伝えきれていないことに常々歯がゆさを感じている。 そのようななか、改訂者全員の大学時代の恩師である渡辺皓先生が執筆くださった本書の改訂に参画する機会をいただいた。本書は、見開きページのなかにポイントがわかりやすくまとめられていて、学生時代に『楽しく解剖を学べた』心地よい感覚が懐かしく思い出された。看護師となったいま、改めて解剖を学ぶ重要性を痛感しており、その想いを込めてNursing Eyeも大幅改訂している。 学生の皆さんには、教科書にある専門用語を機械的に覚えるだけの学問として解剖学をとらえるのではなく、人の身体に興味・関心を寄せ、楽しく学んでくれることを望んでいる。これから看護技術や病態(疾患)を学ぶうえで解剖学的理解に困らないよう、解剖学の講義が終了した後、すなわち実習の場面などでも本書をそばに置いて、何度でも読み返し活用してほしい。 本書をとおして、私たちが学生の時分に感じた解剖を学ぶ楽しさを感じてもらえたら、そして看護師として解剖を学ぶ意義が伝わっていたら、とても嬉しく思う。 2015年12 月 石田 陽子(山形大学医学部看護学科講師)
続きを読む
